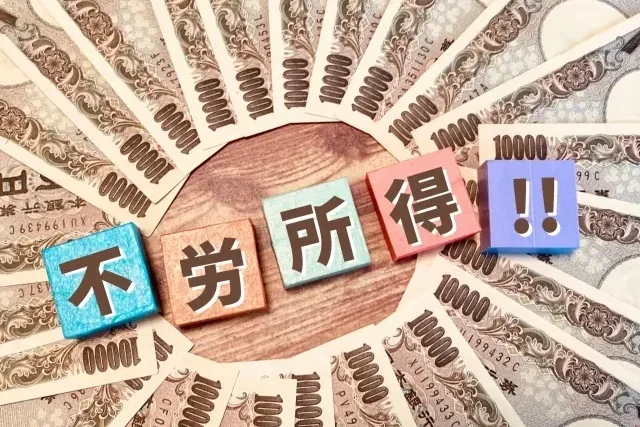5分で分かるサブリースとは?仕組みや注意点をわかりやすく解説!
 運用と管理
運用と管理サブリースをめぐり「保証された賃料が顧客に⽀払われない」などのトラブルが度々メディアに取り上げられています。
その中には大手企業もあり、「大企業だからといって安心できない」と不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
そういったトラブルを防止するため、国⼟交通省は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月公布)」(サブリース新法)のうち、サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施行)について、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を策定しました。
具体的には、以下が義務付けられます。
- 第28条 誇大広告等の禁止
- 第29条 不当な勧誘行為の禁止
- 第30条、31条 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
しかし、本来サブリースとは空室リスクを回避するための手段です。
それがなぜ問題になっているのか、そもそもサブリースとはどのようなものなのか、よく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、賃貸経営を検討されている方に向けて、サブリースの概要と実態、そして契約を利用する際の注意点や問題点について解説します。
サブリースとは、賃貸経営のリスクである”空室リスク”を回避する手段の一つ

サブリースとは、賃貸経営のリスクである空室リスクを回避する手段の一つです。
アパート経営など賃貸経営を行うオーナーからサブリース業者が賃貸物件を借り上げて、転貸します。
サブリース会社は、賃貸物件の入居の有無に関わらずオーナーに保証賃料を支払います。
保証賃料とは、サブリース会社が入居者から受け取っている家賃からサブリース手数料などを差し引いたものでサブリース賃料とも呼ばれます。
これと類似のサービスに、「集金管理代行」というものがあります。
集金管理代行は、文字通り、賃貸物件の入居者からの賃料(以下、本来賃料)回収を代行するサービスです。手数料などを差し引いた後、オーナーに賃料が支払われるという点ではサブリースと似ている点もあります。
しかし、集金管理代行では入居者がいない場合には賃料が発生しないためオーナーは賃料収入を得ることができません。
すなわち、空室リスクを自らがそのまま背負うことになるという点がサブリースとの大きな違いです。
| サブリース | 集金管理代行 | |
|---|---|---|
| 入居者の有無 | 関係なく保証賃料が支払われる | 入居者の有無に応じて賃料収入が異なる |
| 手数料 | 必要(賃料の10~20%程度) | 必要(賃料の3~5%程度) |
| 空室リスク | 回避手段として有効 | 回避することはできない |
サブリースのメリット

では、サブリ―スにはどのようなメリットがあるのかを整理してみましょう。
空室リスク・滞納リスクの回避
サブリースの大きなメリットは、「空室リスクを低下させること」でしょう。
空室が発生すると、見込んでいた賃料収入が得られずアパートローン返済の支払いに回せないなど、キャッシュフローに影響を及ぼします。
一方、サブリースで保証される賃料は、本来賃料よりも下回ることになりますが、入居者の有無に関わらず、サブリース契約に定められた一定の収入(保証賃料)を得ることができます。
これはオーナーにとって大きな安心材料となるでしょう。
賃貸管理業務を一括して任せられる
賃貸経営を行う際、「入居者募集」や「賃貸契約の締結」「家賃回収」「入居者対応」など様々な管理業務が発生します。
サブリースを活用すると、それらの管理業務もサブリース業者に代行してもらえることになります。
手間のかかる管理業務をプロに一括して任せることができるので、特にサラリーマンオーナーはメリットを感じる方も多いのではないでしょうか。
確定申告を簡素化できる
賃貸経営における収入は、不動産所得にあたりますので確定申告が必要です。
しかし、サブリースを活用すると入居に関する管理業務はサブリース業者が行います。
そのため、オーナーは入居者の入退去時にかかる費用などの計上が不要となり、確定申告にかかる収支管理が簡便になります。
サブリースのデメリット

サブリ―スにはデメリットもあります。
したがって、サブリースを検討するにあたっては、デメリットを十分把握した上でメリットに目を向ける必要があります。
家賃収入を最大化できない
賃貸経営において受け取ることができる収入には、賃料収入の他に入退居時の費用の1つでもある礼金や更新料があります(※敷金は預り金)。
しかし、サブリ―スの場合、入居者と賃貸借契約を締結するのはあくまでもサブリ―ス業者なので、礼金や更新料を受け取ることができるのはサブリース業者です。
サブリース契約の内容にもよりますが、サブリースを利用している場合、一般的にはオーナーは礼金や更新料を受け取ることができません。
また、家賃収入も本来賃料を下回る保証賃料となるため家賃収入を最大化することができません。
入居者を選ぶことができない
サブリースを活用すると、サブリース業者が入居者募集や入退去の手続きなどを行うことになります。そのためオーナーが自ら入居者を選ぶことはできません。
サブリース業者は、入居者の有無に関わらずオーナーに保証賃料を支払う必要がありますので、入居者をつけて家賃収入を確保できなければ不足分をサブリース業者が負担しなければなりません。
そのため、サブリース業者によっては入居者審査のハードルを低く設定してでも入居者をつけようとする可能性もあります。
その結果、オーナーとしては好ましく思わない入居者が入居してしまうことがないとも言い切れません。
サブリース会社の倒産リスクがある
サブリース業者が倒産すると、オーナーは保証賃料を受け取ることができなくなります。
サブリース業者が入居者と締結した賃貸契約はオーナーが引き継ぐことになりますが、同時に空室リスクもオーナーに引き継がれます。
また、契約内容にもよりますが入居者情報をサブリース業者がオーナーに報告していない場合もあります。
その場合、サブリース業者から賃貸契約を引き継いだものの、既存の入居者が誰なのか分からなかったり、入居者が引き続きサブリース業者に賃料の振り込みを行ったりといったトラブルが生じるケースもあるので注意しましょう。
サブリースの注意点と問題点
サブリースのメリットとデメリットを踏まえ、サブリース活用時の注意点と問題点について確認しておきましょう。
サブリース契約に費用がかかる
サブリース契約によるサブリース業者が保証する賃料は、本来賃料の80%〜90%とされているのが一般的です。
つまり、サブリースを活用する場合、本来賃料の10%~20%の費用がかかることになります。
ここで、近年メディアにも取り上げられたシェアハウスをめぐるトラブルを振り返ってみましょう。
シェアハウスメーカーは、30年間定額の家賃を保証するとうたって、シェアハウスの販売とサブリ―ス事業を展開していました。
ところが、実際にはシェアハウスの入居率は低く、オーナーに支払う保証賃料より実際の家賃が下回っており、廉価なシェアハウスを高額で販売して得た利益で保証賃料を補填する状態が続いていました。しかし、別のシェアハウスメーカーの破綻をきっかけに銀行が融資をストップ。
すると、シェアハウスの販売ができなくなり資金繰りが悪化、オーナーに保証賃料を支払えなくなり、ついにはそのシェアハウスメーカーは破たんしてしまいました。その結果、シェアハウスのオーナーは保証賃料を打ち切られ、多額のアパートローンと入居率の低いシェアハウスが手元に残ることになってしまったのです。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、サブリース活用を検討する前に少なくとも基礎知識程度は有しておきたいものです。
先程のケースでは、「30年間家賃保証」「空室リスクはない」などとオーナーに説明していたようですが、実はサブリース契約には保証賃料の見直しがあります。
サブリースの契約期間と家賃保証の見直しがある
サブリースのうたい文句として〇〇年保証とパンフレットなどに記載があっても、サブリースの契約書に数年ごとに家賃保証の見直しがあることが明記されているのが一般的です。
サブリース活用の有無を問わず、当然のことながら賃貸物件は永久に新築状態であり続けることはありません。
年数を経ると老朽化し、賃貸物件の魅力が低下する可能性があります。そのため、賃料の引き下げを行わなければ入居者が集まらない時期が来ることも十分に考えられます。
また、周辺に新築の賃貸物件や嫌悪施設が建設されることにより、賃貸需要の変化が生じる可能性もあるでしょう。
そのため、サブリース契約において数年ごとにサブリース賃料を見直す旨が規定されていることは、問題ではなく当然のことと言えます。
ですので、数年ごとに保証賃料の見直しがあることを踏まえた上でもなお、キャッシュフローが悪化しないかどうかをあらかじめシミュレーションしておく必要があります。
なお、契約期間中であっても、更新時期にかかわらずサブリース業者から「借地借家法第 32 条」の規定により賃料の減額や、サブリース契約の解除をされることがあります。
サブリース会社のリサーチ・分析力および集客力に差がある
サブリース会社はどこでも同じではありません。
サブリース会社のリサーチ力、分析力、集客力は、会社によって異なります。オーナーの良いパートナーとなってくれる会社を探すことが大切です。
目先の利益ではなく、オーナーの将来のことも親身に考え、資料提供やライフプランのシミュレーションなどにも真摯に対応してくれる会社を選ぶようにしましょう。
アパート経営のサブリースとマンション経営のサブリースの違い
ちなみに、「サブリース」と同じ意味合いで使われる「一括借り上げ」という言葉がありますが、厳密に言えその意味合いは異なりますのでよく理解しておきましょう。
マンション経営のサブリース
マンション経営の場合は、1部屋ごとにサブリースを行うことが一般的です。
複数のマンションを所有している場合で、1部屋ごとにサブリースの活用有無を使い分けることもできます。
アパート経営のサブリース
一方、アパート経営のサブリースは、アパートの全室を対象とすることが一般的です。
サブリース会社が全室を借り上げることから、「一括借り上げ」と称されます。一括借り上げの場合、建物のメンテナンスなども一括して行うことが条件となっている場合もあります。
解約時のトラブル
サブリース業者とオーナーは、一般的に普通借家契約に基づいてサブリース契約を締結します。
この場合の貸主はオーナー、借主がサブリース業者となります。
普通借家契約は、契約期間満了後は借主が引き続き契約更新を希望する場合、原則として同条件で契約が更新されることになります。
オーナーは、原則として正当事由がなければ更新を拒絶することはできません。
なお、オーナー、サブリース業者、双方から賃料の見直しを請求することも認められています。
サブリースの契約は原則、借地借家法によりオーナーから解約ができません。
しかし、サブリース業者からの中途解約は、特段の事由がなかったとしても行うことができます。
なお、中途解約条件を契約書で定めていて、正当な理由があると認められる場合にはオーナーからの解約ができる可能性もありますが、中途解約条件の有無にかかわらず、オーナーからの解約に対して借地借家法で要求される条件は厳しいので注意が必要です。
あらかじめよく認識すると共に、十分注意してください。
サブリース以外のサービス

サブリース以外にも、オーナーをフォローするサービスがあります。様々なサービスがあることを知った上で必要に応じた選択を行いましょう。
管理委託
管理委託とは、賃貸経営に関わる管理業務を代行してくれる委託サービスです。
パッケージ化されたサービスを提供している会社もありますし、必要な管理サービスをメニューの中から選ぶことができる会社もあります。
滞納保証
このサービスは賃貸借契約中の滞納家賃を保証するものです。
家賃滞納者から回収を行うことは、想定している以上に手間がかかり、対応が遅いと数か月分の滞納となり、滞納家賃を回収不能となるケースがあります。
そこで、入居者の家賃滞納の対策として、入居者に家賃保証会社と契約を締結してもらい、万が一、ある入居者が決められた期日までに家賃の支払いを行わなかった場合、家賃保証会社が立て替えてオーナーに滞納分の家賃を支払ってもらいます。
まとめ
サブリースは、空室リスクを回避することができるなどオーナーをフォローする仕組みが整っています。
しかし、内容をよく理解していなければ「こんなはずじゃなかった……」と、頭を抱えることになりかねません。
目先の利益だけを見るのではなく、長期的な視点を大切に収支計画の作成 とシミュレーションを行った上でサブリースを利用するかどうかじっくりと検討することをおすすめします。
この記事のキーワード Target Keywords

監修:小泉 由貴乃(レイビー編集長)
管理業務主任者、マンション管理士、3級ファイナンシャル・プランニング技能士

監修:東海林 康太(賃貸管理の専門家)
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士